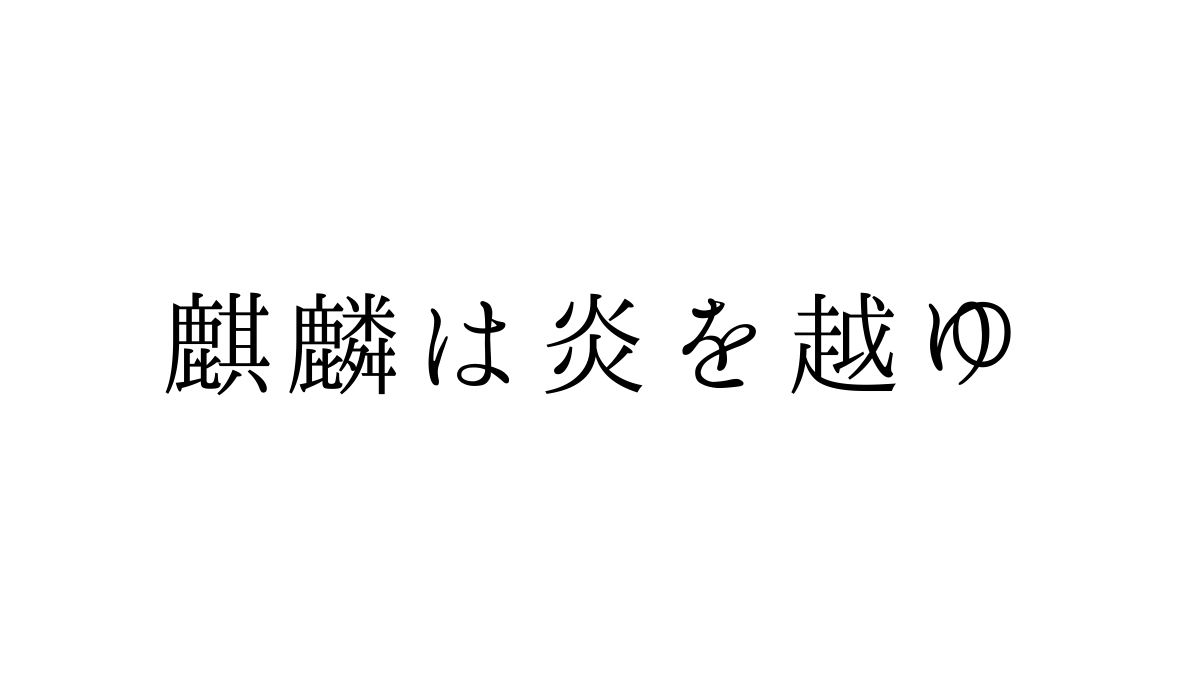天正十年、初夏。京の都は深い闇と、じめりとした熱気に包まれていた。湿度をたっぷり吸い込んだ空気は重く、肌にまとわりつく。土壁の向こうから聞こえる虫の合唱は、この時代の変わらぬBGMでありながら、今宵はどこか切迫した調子を帯びているように感じられた。
九条朔は、土塀の影に身を潜め、呼吸を整えていた。彼の装束は、この時代にしては不自然なほどに黒く、夜の闇に溶け込んでいた。鼻腔をくすぐるのは、馬糞と湿った藁の匂い、そして古びた木材が放つ埃っぽさ。しかし、彼が今最も意識しているのは、手のひらの中で鈍い光を放つ、掌サイズの『転写体』だった。未来永劫、秘匿されるべき情報が詰まった、わずか数グラムの記録媒体。
「目標座標、間もなく到達。京都、本能寺。歴史分岐点まで、残り二刻」
耳元で微かに電子音が響く。朔は冷や汗を拭った。この時代へ転送される際に被った肉体的な負荷はまだ残っている。強烈な時間のねじれに晒された影響で、彼の胃の奥は酸っぱい痛みを訴えていた。
彼の任務はただ一つ。織田信長の死を阻止すること、ではない。歴史の整合性を守ること、でもない。彼の任務は、特定の条件を満たす情報開示により、この時代に一つの『楔』を打ち込むこと。それが、彼が所属する組織の遠大な計画の第一歩だった。
彼は壁からそっと顔を出し、本能寺の周囲を見渡した。松明の赤く揺らめく光が、門前の石畳に不規則な影を落としている。警護の足軽たちの会話が、夜の静寂を破って微かに聞こえてくる。彼らの声は、警戒心の高さと、主君に対する畏怖とが混ざり合った、硬い響きを持っていた。
朔はため息を押し殺した。もし失敗すれば、彼はこの時代に置き去りにされ、存在そのものが時間軸の塵となる。しかし、未来を変えるという重みが、彼の脚を動かした。
本能寺の内部は、外の喧騒とは隔絶された静謐な空間だった。広間の一角、わずかな蝋燭の灯りの下で、織田信長は鷹揚に胡坐をかいていた。彼は上質な白練の小袖を纏い、目の前には、遠くから献上されたばかりの唐物茶碗が置かれている。
「で、伊勢守。越後からの報告は、真であるか」
信長の低い声が響く。それは感情の起伏を感じさせない、しかし刃物のように鋭い響きを持っていた。対座しているのは、近習の一人、森蘭丸である。
「はっ。上杉景勝、いまだ不穏な動きを見せております。柴田様からの書状によれば、一向に攻め手の準備を緩めてはならぬと」
蘭丸の声はまだ若いが、その言葉遣いには信長に仕える者としての厳しさが宿っている。信長は茶碗を手に取り、その艶やかな表面をじっと見つめていた。
「景勝か。あの男、何を考えているのやら。猿めが上手くやっているというに」
信長はふと、遠い目をしながら茶を啜った。その時、障子の外から、微かな物音が聞こえた。警護の武士が異変を察知し、ざわつく気配。
「なんだ、騒々しい」
信長は不快そうに顔を顰めた。
障子が一瞬、勢いよく開きかけ、そしてすぐに数名の武士によって制圧される音が聞こえる。怒声、そして何かが畳の上を滑る音。そして、静寂。
蘭丸がすぐに立ち上がり、鋭い視線で障子を見据えた。
「不届き者が侵入しようとした模様。すぐさま首を刎ねさせます」
「待て」
信長は手を挙げた。その制止の仕方は、音もなく、しかし絶対的な重さを持っていた。信長はゆっくりと、顔を傾けた。彼の横には、警護の武士が先ほど抑え込んだ際に取り落としたと思しき、黒光りする奇妙な物体が転がっていた。
それは、この時代には存在し得ない、滑らかな金属と硬質な樹脂でできた、手のひらに収まる箱だった。周囲の松明の光を反射し、鈍く光っている。
信長は立ち上がった。彼の歩みは静かで、しかし、その一歩一歩が重力を増していくかのように感じられた。彼はその物体を拾い上げ、指先で感触を確かめた。冷たい。そして、継ぎ目が一切見当たらない、異様な加工精度。
「これは……異国の道具か」
信長が呟く。その声には、怒りよりも、純粋な好奇心が混ざっていた。
朔は既に捕らえられていた。背後で両腕をきつく縛られ、口には手ぬぐいが押し込まれている。彼は全身から血の気が引くのを感じていた。彼はただ、転写体を信長の手元に届けることだけに集中し、警護を突破する際に深手を負った。だが、転写体は彼の身体から離れた。任務は、かろうじて成功したのだ。
信長は、転写体のスイッチのような部分を、無意識に撫でた。瞬間、その箱は振動し、信長の目の前の闇に向けて、鮮やかな光を放ち始めた。
蘭丸が驚愕の声を上げる。
「殿! そ、それは!」
広間の空気そのものが震え、突如として空間の中に、ありえない映像が展開された。それは、立体的なホログラムだった。
信長は、その映像の中に、自分自身を見た。だが、その信長は、彼の知る未来よりも、遥かに年老いて、豪華絢爛な甲冑を身に着けていた。背景には、見たこともない巨大な城郭。石垣は数段にも重なり、天を衝くような天守閣。
「安土城、か? 否、これは……」
信長は息を呑んだ。
映像は目まぐるしく変わる。巨大な鉄の船が海を渡る様子。空を飛ぶ鉄の鳥。人々の暮らしは、彼の想像を絶する豊かさと技術に満ちていた。
「これが、余が築く未来か……」
信長は感嘆し、そして、微かに笑った。
しかし、映像は唐突に、赤と黒の、不穏な色調に染まった。
信長は次の映像に釘付けになった。それは、炎に包まれた本能寺の全景だった。炎の熱が、映像を通して信長の肌にまで届くように錯覚させる。黒煙は夜空を覆い、その中で、彼自身が、血を流し、絶望的な眼差しで倒れ伏している姿が映し出された。
蘭丸は言葉を失い、恐怖で体が硬直していた。この映像が、未来の予言であること、そして、それが主君の死を意味していることを、本能で理解したからだ。
映像はさらに続く。炎の中で、信長の命を奪った張本人として、一人の武将の顔が、大きくクローズアップされた。その男は、悲しみと、狂気に満ちた、複雑な表情を浮かべていた。
その名は――明智光秀。
信長は、その名を脳裏で反芻した。光秀。日向守。余の寵愛を受けた、あの男が。
ホログラムはそこで消え、転写体は再び、ただの冷たい金属の塊に戻った。広間には、蝋燭が燃える音と、信長の荒い呼吸だけが響いていた。
信長は、転写体を握りしめたまま、その場に立ち尽くしていた。彼の内面では、驚愕、怒り、そして理性的な分析が、嵐のように渦巻いていた。
(異国の術か? いや、術にしては、あまりにも緻密すぎる。光秀、あの男が余を裏切る? ありえぬ。彼は余の掲げる天下布武の旗の下、最も忠実に働いてきた。しかし、あの目……あの絶望と狂気が混じった目は、偽りではない。)
信長はゆっくりと、背後に縛られている朔に向き直った。朔は、口枷のせいで言葉を発せないが、その瞳は必死に訴えていた。信長は一歩近づき、朔の耳元で囁いた。
「貴様は何者だ。何を目的として、このような奇術を見せた」
朔は身悶えし、口枷越しにかすれた声を漏らしたが、言葉にはならなかった。信長は諦め、再び蘭丸に向き直った。
「蘭丸。貴様は、今の映像をどう見た」
蘭丸は震える声で答えた。
「恐れながら、殿。あれは悪夢にございます。しかし、明智殿が……まさか」
「まさか、か」
信長は鼻で笑った。
「余は昔から、『まさか』という言葉が大嫌いだ。この世に起こり得ないことなど存在しない。だが、あの映像が真であるならば、余は今宵、死ぬ。この本能寺で、光秀の手によって。天正十年六月二日、未明に」
信長は座り直し、茶を一口啜った。驚くほどに、彼の心は急速に冷静になっていた。天才は、危機的状況においてこそ、その真価を発揮する。彼は既に、この危機を乗り越えるための道筋を探り始めていた。
「光秀は今、丹波亀山城にいるはず。備中への援軍と称して、余の命を待っている。だが、奴めは既に動いている。あの映像が真ならば、今頃、謀反の兵を率いて京を目指しているだろう」
蘭丸は顔面蒼白になった。
「すぐさま、近習を集め、防備を固めさせます!」
「遅い」
信長は冷徹に言い放った。
「光秀は緻密な男だ。余の周りには、わずか百の手勢しかおらぬ。城郭でもないこの寺院で籠城しても、数に勝る光秀の兵に包囲されれば、火を放たれるのがオチだ。映像の通りにな」
信長は顎に手を当て、深い思索に沈んだ。彼の思考は、既に未来の自分を乗り越え、光秀の次の一手を読み解こうとしていた。
「蘭丸よ。すぐさま、二条御所にいる信忠に文を届けさせよ。内容は極秘。本能寺の変は起こさせぬ。この寺をすぐに出る。そして、この異国の道具を見せた者――こやつも連れて行く」
――同時刻。丹波亀山城を出発した明智光秀は、大軍を率いて京へと向かっていた。夜の湿気と霧が、騎馬武者たちの呼吸を白く染める。光秀の顔は、周囲の闇以上に暗く、そして青ざめていた。
(殿を討つ。この手で、天下の主を討つ)
光秀は、胸の奥で渦巻く感情を、必死に抑え込んでいた。この謀反は、彼にとっての究極の忠義であり、究極の裏切りでもあった。信長の苛烈な要求、過度な懲罰、そして、天下統一という名の暴走。光秀は、信長が己が道を踏み外したと考えた。麒麟児を正すには、この方法しかないと、己に言い聞かせ続けた。
「日向守様、もうすぐ老ノ坂を越えまする」
側近が囁いた。
「うむ」
光秀は短く応じた。老ノ坂を越えれば、京はすぐそこだ。そして、本能寺。信長が、わずかな手勢とともに無防備に宿をとっている場所。
光秀は、馬の蹄の音、鎧の擦れる音、兵士たちの低い息遣い、それら全てを、己の決意を固めるための鎮魂歌として聞き入っていた。
(信長公よ。あなたはあまりにも遠くへ行き過ぎた。わしは、わしは……あなたの天下を終わらせる)
彼の目に、涙が滲んだ。この悲劇的な決断に至るまでの数ヶ月間の苦悩が、今、老ノ坂の冷たい霧となって、彼の顔を覆っていた。
「全軍に伝えよ。目標は本能寺。敵は、織田信長ただ一人!」
光秀の宣言が、闇夜に響き渡った。兵士たちの間には、多少の困惑が見られたが、長年の訓練により、彼らは主君の命令に従い、京へと急いだ。
――本能寺は、静かだった。静かすぎた。
午前三時。光秀軍の先鋒が本能寺を包囲し始めた際、異様な静けさに気がついた。通常であれば、警戒の物音や、緊張感のある気配が伝わるはずだ。だが、寺全体が深い眠りについているかのように、何もかもが静まり返っていた。
光秀は、寺の門前で馬を止め、不安そうに眉をひそめた。土塀越しに嗅ぐ匂いは、古い木と土の匂いだけであり、人の活動の匂いがしない。
「どうした。なぜ、火の手を上げぬ」
光秀は苛立ちを露わにした。
手練れの先鋒が、門を蹴破って内部を確認し、すぐに戻ってきた。その顔は、困惑と恐怖に歪んでいた。
「は、日向守様……。本能寺には、誰もおりません」
光秀は耳を疑った。
「馬鹿な! 警護の者も、近習の者もか!」
「はい。床は、まだ温かいように思われましたが、すでに主だった者たちの姿は、どこにも……まるで、煙のように消え去ったようでございます」
光秀の頭の中が、真っ白になった。彼の全身から力が抜け、鞍の上で大きく揺れた。緻密に練り上げられた、失敗の許されない大計画。その最重要目標である織田信長が、忽然と消滅した?
(なぜだ。なぜ、殿は……この期に及んで、本能寺を離れたのだ? まさか、この計画が漏れたというのか?)
光秀は即座に、二条御所にいるはずの信長嫡男、織田信忠の元に兵を差し向けさせた。しかし、そこからも同様の報告が届いた。二条御所も既に、信忠と近習たちが撤退した後だった。
謀反は、空振りした。歴史は、ここで決定的に捻じ曲げられたのだ。光秀は、老ノ坂から見下ろす京の闇に向かって、激情の混じった呻きを上げた。
「織田信長! 貴様は、いかなる術を用いたのだ!」
本能寺から脱出した信長の一行は、九条朔を護衛代わりに引き連れ、わずか二刻で京から脱出していた。
馬上で、信長は静かに朔に問いかけた。朔は、口枷を外され、憔悴しきった表情で、震える声で答えた。
「私は、歴史の整合性を……維持するために送られた者です。殿の死は、歴史上、必須事項でした。ですが、私の属する組織は、その必須事項に、干渉する道を選んだのです」
信長は笑った。それは、冷酷な勝利の笑みだった。
「歴史の整合性か。面白くもない。歴史など、余が作り変えてこそ、意味があろう」
信長は、夜明けの東の空を見上げた。夜の闇は払われつつあるが、この夜の出来事によって、日本の歴史は、永劫に変わってしまった。本能寺の変は起こらず、麒麟児は生き延びた。
「朔よ。あの映像が真ならば、光秀は余を討てなかった今、どのような動きを見せると思う?」
朔は、未来の知識を絞り出し、答えた。
「光秀は、京を占領し、天下を望むでしょう。ですが、彼は信長様の生存を知れば、必ずや動揺します。そして、羽柴秀吉、柴田勝家など、他の大名が光秀を討つべく、迅速に動くはずです」
「秀吉か。あの猿めが、また天下を狙うか」
信長は皮肉を込めて言った。だが、彼は既に、この危機を、天下統一への加速剤として利用する方法を考えていた。
「蘭丸。今すぐ、西国へ向かえ。羽柴秀吉へ、余が生存していることを伝えよ。光秀を討ち取るならば、褒美は望むがままに与えるとな。だが、条件がある」
蘭丸は恭しく頭を下げた。
「いかなる条件にございましょうか」
信長の目には、未来の知識と、彼の持つ圧倒的な野心が交差していた。彼は、朔がもたらした未来の技術を、今後どう利用するか、既に計画を立て始めていた。
「光秀を討ち取った後、猿は天下を欲するだろう。それを許さぬ。余は、この九条朔という男と、彼が持ってきた『未来の知識』を使って、光秀よりも早く、天下を統一する。そして、猿に、天下の重荷を背負わせる前に、余の絶対的な支配を確立する。これこそが、余が望む、真の天下布武だ」
歴史改変は、信長の死を防ぐだけにとどまらなかった。それは、彼に未来を見通すという、神の視点を与えてしまったのだ。日の光が、東山を照らし始め、信長の顔を強く照らした。彼の顔には、死の恐怖など微塵もなく、新たな世界を切り開く者としての、絶対的な自信が満ち溢れていた。
歴史は、天正十年六月二日、完全に新たな道筋を辿り始めた。織田信長の生存は、日本全土に、激しい動揺と、これまで想像もつかなかった変革の嵐を巻き起こすだろう。
(歴史の整合性? 知ったことか。この世は、常に余が作り変えるものだ)
信長は、朔が持ってきた未来の道具をポケットにねじ込み、馬を京とは逆方向、すなわち、未来の技術を導入するのに適した領国へと走らせた。彼の背後で、明智光秀の謀反は、歴史の表舞台から、ただの「裏切り者の愚行」として、消え去ろうとしていた。
(了)