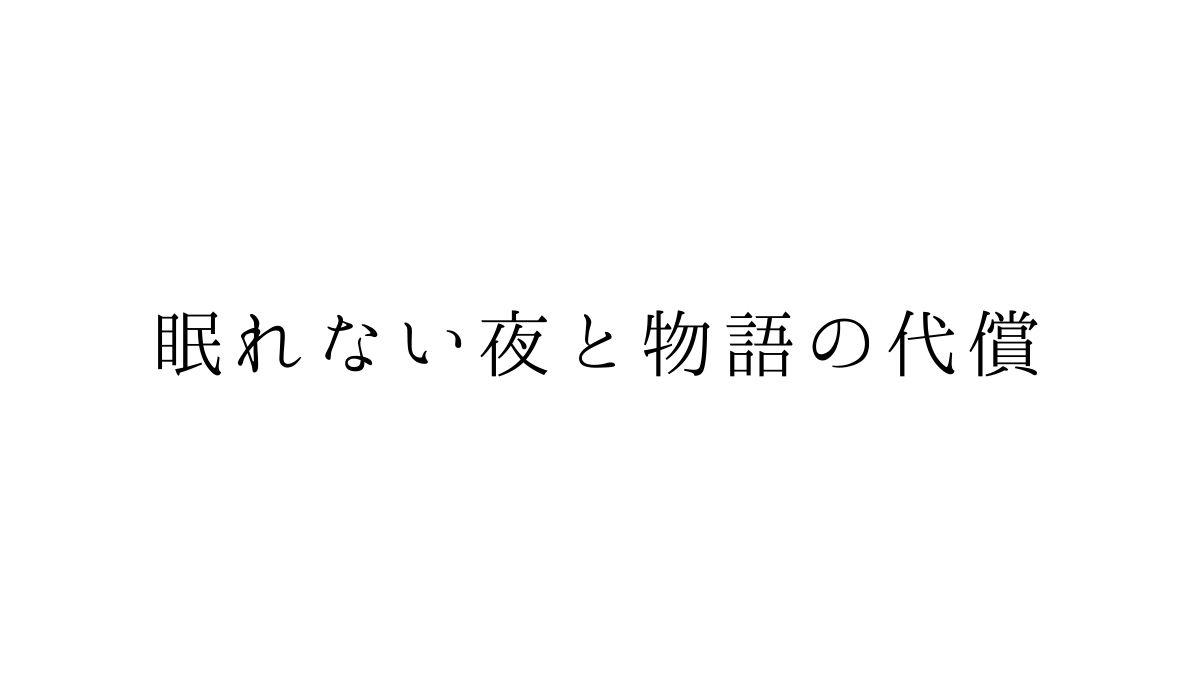小説を真剣に描き始めてから、眠り方を忘れてしまった気がする。
布団に入ると、体は確かに疲れているのに、頭の中だけが蛍光灯の下に取り残されている。さっきまで書いていた一文が、改行の位置が、あの台詞が本当に正しかったのかどうかが、いつまでも脳内でリフレインする。画面を閉じても、物語は閉じられない。その続きが、勝手に頭の中で書き足されていく。
日中、ようやく捻り出した台詞を消しては打ち直し、プロットをいじり倒した末に「今日はここまで」と決める。パソコンを落として、部屋の灯りも落とし、「明日の自分、あとは頼んだ」と心の中でつぶやく。
だが、そこからが本番だ。布団に横たわると、さっきまで沈黙していた登場人物たちが、急に饒舌になり始める。「あのシーンで、あんなこと言わないよ」「むしろ、こう怒るはずだろ」「あの設定、矛盾してない?」。書いているときは出てこなかった違和感が、夜になると一斉に立ち上がる。
そしてこちらも、「それいいね」とか「たしかに変だったかも」と返事をしてしまう。対話が成立してしまった時点で、眠気はどこかへ行く。明かりをつけてメモするか、このまま覚えておくかで迷い、結局スマホを取ってメモアプリを開く。画面の光が、残っていた眠気を完全に焼き払う。
小説を「趣味」ではなく、少なくとも自分の中で「本気の仕事」として扱い始めた瞬間から、優先順位の配列が変わった。
健康より、締切。睡眠より、「今、掴んでいる感触」。明日のコンディションより、「この一文を今日決めたい」という欲求。
本来、創作と生活は両立させるべきものだとわかっている。だが、物語が一番熱を帯びるのは、たいてい「そろそろ寝なきゃ」と思った後の時間帯だ。静まり返った部屋で、自分のキーを叩く音だけが響くあの感覚は、昼には得られない。
「今日はさすがに寝よう」と思っても、「ここだけ書いてから」「このシーンのラストだけ」と、つい延長戦を重ねてしまう。
そうして気づけば、睡眠時間は削れ、翌日の自分が、前日の自分の熱に付き合わされることになる。
不眠症気味になって一番やっかいなのは、眠れない理由が「つらさ」だけではなく、「楽しさ」と混ざっていることだ。
書くことは苦しい。完成形と現実の文章とのギャップに絶望するし、「自分には才能がない」という声も、夜になるほど大きくなる。けれど同時に、書けているときの興奮は、他の何にも代えがたい。キャラクターが自分の想定を超えて動き出した瞬間、物語のラインが一本につながった手応えを感じた瞬間、胸の内側からカフェインを直接注ぎ込まれたみたいに目が冴える。
不安で眠れないのか、興奮で眠れないのか、自分でも判別できなくなる。どちらにせよ、頭はフル稼働している。体だけが取り残されて、「そろそろ休ませてくれ」と悲鳴を上げている。
眠れない夜を重ねていても、「じゃあ今日は書くのをやめて早く寝よう」とは、なかなかならない。そこには、「書かない自分」に対する強い罪悪感があるからだ。
一度「真剣に小説を書く」と決めてしまうと、「書かなかった日」が、まるで自分の夢を裏切った日みたいに感じられる。SNSで「毎日◯時間書いてます」という誰かの投稿を見ると、まだ見ぬライバルたちの足音まで聞こえてくる気がする。「書いてない間にも、誰かは書いている」と思うと、布団に入っている自分がひどく怠惰に見えてしまう。
だから、無理やりパソコンを起動する。眠れないなら書けばいい、と開き直る。こうして「不眠」と「執筆」が、互いを悪化させ合うループができあがる。
では、不眠症気味になってまで小説を書く価値はあるのか、と問われたらどうだろう。
正直なところ、「健康のほうが大事ですよ」と言われたら、その通りだと思う。実際、書き詰めて体調を崩し、一文字も書けない期間が続くことほど、無意味な消耗はない。
それでもやめられないのは、書くことが「生産活動」以上の意味を持ち始めているからだ。
書いていないと、自分が自分でないように感じる。書けていない期間が続くと、「生きているのに、何も残せていない」ような焦りに襲われる。
眠りを削ってまで物語にしがみつくのは、たぶん小説が「作品」である以前に、自分にとっての「証明」だからだ。
自分が考えたこと、自分が見てしまったもの、自分だけの痛みや憧れを、何かの形にしておきたい。その切実さが、睡眠欲より強くなってしまう夜がある。
不眠症気味になって、ようやく気づいたことがある。
「眠らないで書く自分」ではなく、「眠りながら書き続けられる自分」を、長期的には目指さないといけない、ということだ。
徹夜の文章には、たしかに独特の冴えがある。だが、推敲の段になって読むと、「この一文を直すだけで、一晩寝られたのでは?」と思うことも多い。冷静さと体力は、物語にとっても資源だ。
だから最近は、せめてこんなふうに考えるようにしている。
「今日は、物語のために寝る」
眠ることを「書かない逃げ」ではなく、「より長く書くための準備」に位置づけ直す。それでも布団で物語が動き出したら、メモを一行だけ書いて、そこで打ち切る。続きは、明日の自分に譲る。
小説を真剣に描き始めて、不眠症気味になった。それは、物語に人生を侵食されつつある兆候でもあり、ようやく本気になれた証拠でもある。
この先きっと、眠れない夜は何度もやってくる。それでもいつか、「よく寝て、よく書く」という当たり前のリズムを、物語と一緒に手に入れられたらいいと思う。
その日までは、まぶたの裏で動き続ける登場人物たちと、少し不器用な同居生活を続けていくしかないのだろう。
(了)