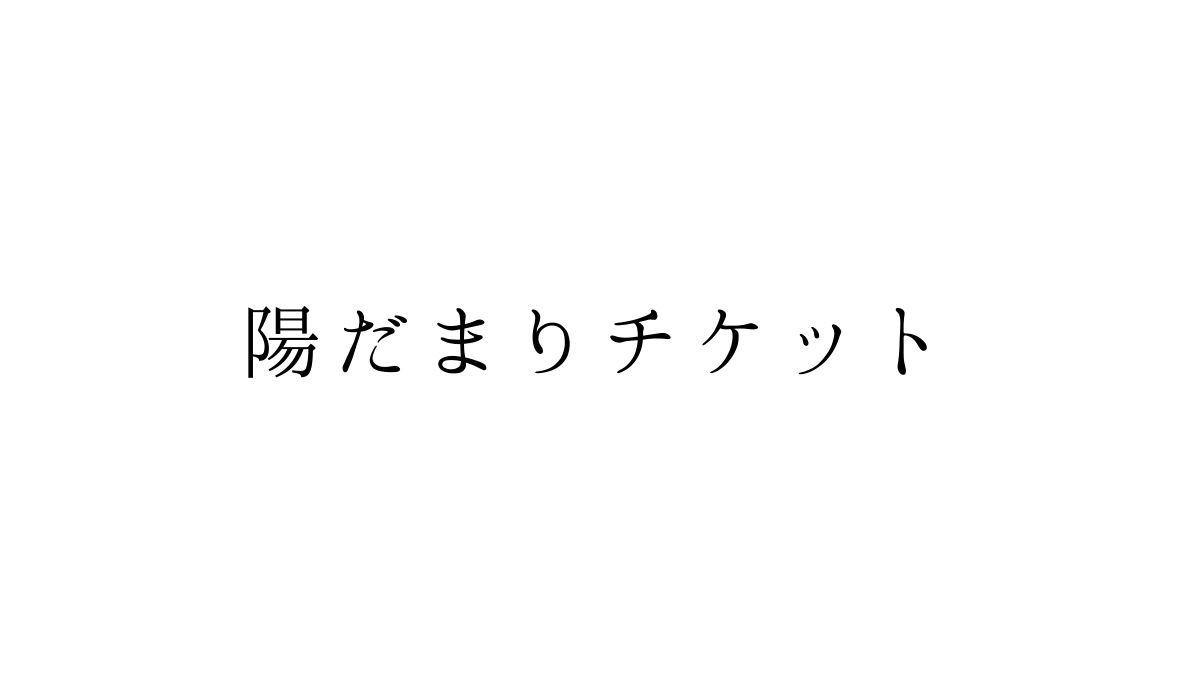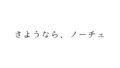カーテンの隙間から差し込む光の粒が、ふわりと宙を舞っている。目が覚めたとき、最初に感じたのはコーヒーの深くて優しい香りだった。
加奈子は、枕に顔をうずめたまま、ゆっくりと深呼吸をする。日曜日の朝。時計の針はまだ九時を回ったばかり。隣を見ると、シーツには彼が抜け出した後の温もりだけが残っていた。
キッチンの方から、トントンというリズミカルな包丁の音と、何かがジュワッと焼ける音が聞こえてくる。そして、鼻歌まじりの低い声。
「……ふふ」
思わず笑みがこぼれた。同棲を始めて二年。彼は料理が得意なわけではないけれど、休日の朝だけは「俺の当番だから」と言って、キッチンに立つのが二人のルールになっていた。
ベッドから抜け出し、素足でフローリングを歩く。リビングのドアを少しだけ開けて覗くと、少し大きめのエプロンをつけた彼――春明の背中が見えた。
「あ、起きた?」
気配に気づいたのか、春明が振り返る。その笑顔は、窓から入る日差しよりも眩しくて、加奈子の胸の奥をぎゅっと掴んだ。
「おはよう、春明。いい匂いだね」
「おはよう。今日はね、自信作だよ」
テーブルに並べられたのは、少し焦げ目がついたフレンチトーストと、彩りの不揃いなサラダ。そして、湯気を立てるマグカップ。それは整った朝食とは言い難いけれど、加奈子にとっては世界で一番贅沢な食卓だった。
「いただきます」
一口食べると、甘い卵液の味が口いっぱいに広がる。「どう?」と心配そうに覗き込む春明に、加奈子は大きく頷いた。
「すごくおいしい。今までで一番かも」
「よかった! 隠し味にバニラエッセンス入れたんだよ」
得意げに笑う彼を見て、加奈子はふと、テーブルの隅にある小さな紙切れに気づいた。コースターの下に挟まっている。
「ねえ、これなに?」
「ん? ああ、それ」
春明は少し照れくさそうに頬をかいた。
「今日のデザート代わり」
加奈子がその紙を手に取ると、そこには彼の下手くそな字で、こう書かれていた。
『何でも言うこと聞く券――有効期限:おじいちゃんおばあちゃんになるまで』
思わず吹き出してしまった。
「なにこれ、子どもみたい」
「いいじゃん。昨日の夜、ふと思いついたんだよ。加奈子、最近仕事忙しそうだったから」
春明はマグカップを手に取り、少し真面目な顔をして続けた。
「旅行に行くとか、高いものを買うとかもいいけどさ。俺、加奈子が『あー、幸せ』って思う瞬間を、これから先もずっと、一番近くで作っていきたいんだよね」
その言葉は、どんなプロポーズよりも甘く、加奈子の心を満たしていった。
有効期限、おじいちゃんおばあちゃんになるまで。それはつまり、一生ということだ。
加奈子はチケットを大切に胸ポケットにしまった。
「じゃあ、さっそく使っていい?」
「お、いいよ。何でも」
加奈子は少し身を乗り出して、テーブル越しの彼に向かって言った。
「来週の日曜日も、その次の日曜日も、こうして春明と一緒に朝ごはんが食べたい」
春明は一瞬きょとんとして、それから今日一番の優しい顔で笑った。
「チケット使うまでもないじゃん」
「いいの。これが一番の願い事だから」
二人の笑い声が、陽だまりの中に溶けていく。特別なことは何も起きていない。ただ、朝ごはんを食べているだけ。でも、ここには確かな永遠があった。
これから先、雨の日も風の日もあるだろうけれど、このチケットがある限り、そして彼が隣にいる限り、きっと大丈夫。
加奈子はもう一度、甘いフレンチトーストを口に運んだ。その味は、どこまでも幸せな未来の味がした。
(了)