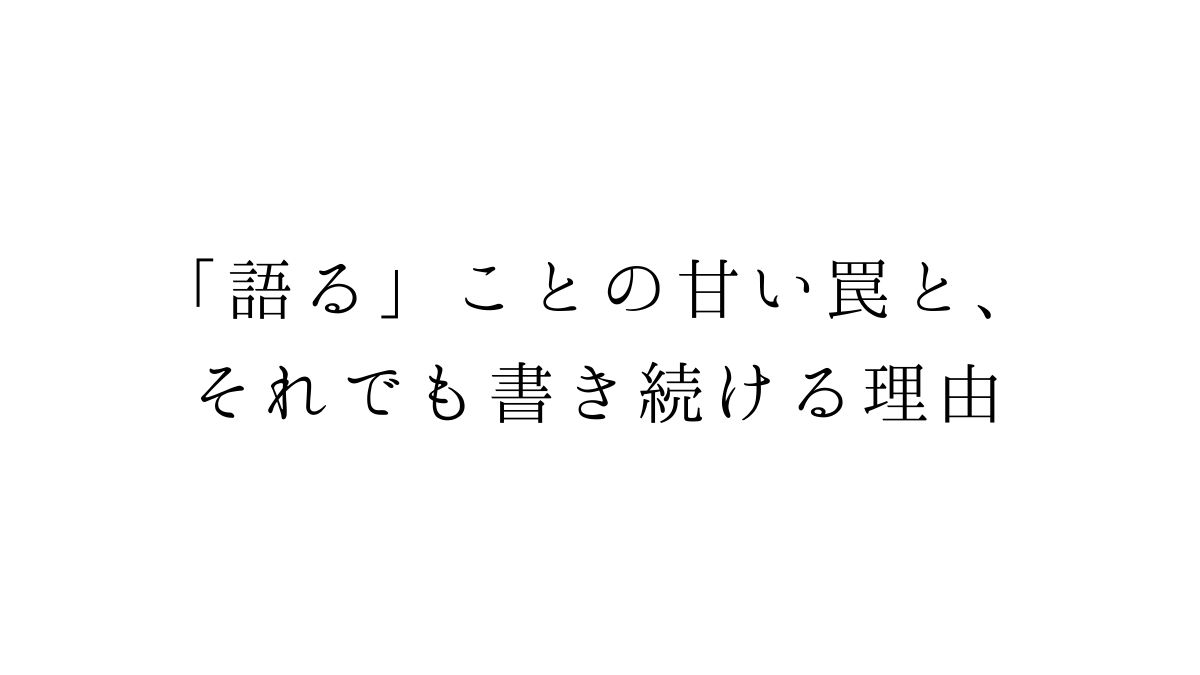「作ることについて語り始めたら、作り手としては終わりだ」
最近、SNSを見ていたら、そんな言葉を目にしてしまった。
その理屈でいくならば、私はとっくの昔に「終わっている」人間だ。このブログを読んでくださっている方ならご存知の通り、私はここで小説やエッセイを発表するだけでなく、「物語の構造とは」だの「エッセイの書き方」だの、あるいは「あのアニメの演出意図は」だのと、まさに「作ることそのもの」について饒舌に語り続けているからだ。
純粋な「作り手」であるならば、作品そのもので語るべきだ、という意見は痛いほどよく分かる。制作の裏側、技術論、あるいは精神論。そういったメタな視点を持ち出した瞬間、物語の魔法は解け、無骨な骨組みが露わになる。手品師が自らタネ明かしをしながら舞台に立っているようなものかもしれない。
「語る」ことは、ある種の逃避だ。生みの苦しみから逃れ、理論という安全地帯から創作を眺めるのは、確かに心地が良い。真っ白な原稿用紙と格闘して血を流すよりも、「良い文章とは何か」を分析して頷いている方が、何倍も楽で、何倍も「やった気」になれる。その甘美な誘惑に負け、私はいつしか「書く人」から「書くことについて書く人」へとスライドしてしまったのではないか。そんな不安がよぎる夜もある。
けれど、と私は思う。本当にそれで「終わり」なのだろうか?
私が「執筆のヒント」を書くとき、あるいはアニメ作品を深く分解してレビューするとき、そこにあるのは「創作からの逃避」だけではないはずだ。むしろ、あまりにも創作という行為が好きすぎて、その構造、仕組み、美しさを骨の髄までしゃぶり尽くしたいという、少し歪んだ愛着なのではないかと思う。
美味しい料理を食べたとき、「美味しい」と完食するだけでは飽き足らず、「この隠し味は何だ?」「どういう火加減ならこの食感になるんだ?」と厨房を覗き込みたくなる。私にとって「作ることについて語る」とは、そういう探究心の延長線上にある。
分解し、分析し、言語化する。その過程で魔法は一度解けるかもしれない。しかし、バラバラになった部品をもう一度自分なりの手つきで組み上げたとき、そこには以前とは違う、より強固で意識的な「魔法」が宿るような気がしているのだ。
だから私は、恐らくこれからも語り続ける。小説の書き方を語り、他者の作品を解剖し、その合間に自らの作品を紡ぐ。もしそれが「作り手としての終わり」を意味するのだとしても、私はその「終わった後の世界」で、しぶとく手を動かし続けていたいと思う。
「語る」こともまた、私にとっては広義の「作る」ことの一部なのだから。
(了)