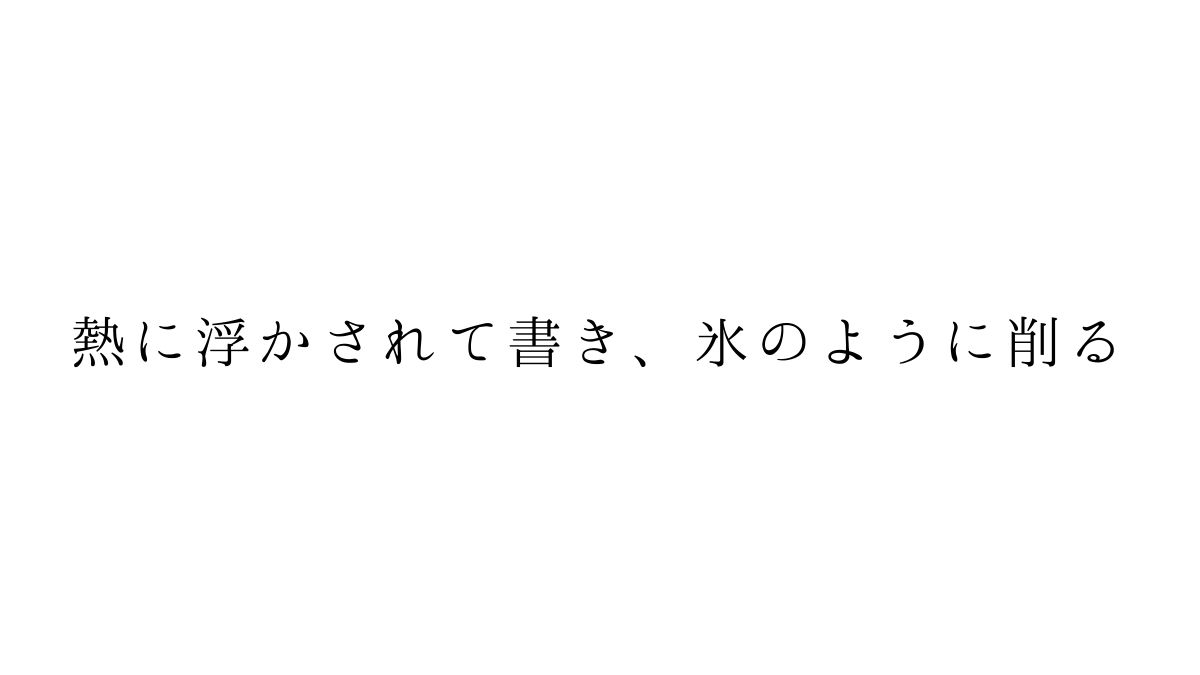ふと思い立って、ファンタジー小説なるものに手を出してみた。これまで読みふけってきたような、あるいは少しばかり気取って書いてきたような堅苦しい文章とは違う。剣と魔法、異世界と冒険。そんな世界なら、もっと自由に、もっと軽やかに言葉が紡げるのではないか。そんな安易な予感があった。
書き始めてみれば、それはまさに奔流だった。頭の中に次々と浮かぶ情景を、キーボードを叩く指が追いかける。畏まった表現も、厳密な考証も、この際すべて後回しだ。「ラノベ」という器は、私の勝手な思い込みによって、どこまでも寛容な受け皿となっていた。やっぱり、肩肘張った文章よりもこっちのほうが性に合っているのかもしれない。勢いそのままに筆を走らせ、気づけばあっという間に十万文字という大台に乗っていた。画面の向こうには、壮大な物語が完成した(かのような)達成感だけが輝いていた。
しかし、小説という魔物が牙を剥くのは、書き上げた後なのだと思い知る。熱が冷め、一人の読者としての冷静な目を取り戻した数日後、私は自分の原稿と対峙した。そこにあったのは、物語の贅肉、重複する描写、勢いだけで押し切ろうとする空虚な会話の山だった。
推敲とは、なんと残酷な作業だろうか。熱量だけで膨れ上がった風船に、論理という針を突き立てていく。ここは説明過多、ここは情景が浮かばない、この台詞はキャラクターが喋っているのではなく作者が喋っているだけだ。削って、直して、また削る。愛着のあったはずのフレーズも、物語のテンポを阻害するなら容赦なく切り捨てた。
そうして一通りの推敲を終えたとき、私の手元に残ったのは五万文字だった。
十万文字の熱狂は、五万文字の静寂へと姿を変えていた。半分である。あの夜、私が打ち込んだ文字の半分は、物語を形作るための足場に過ぎなかったのか、あるいは単なる熱の燃えカスだったのか。
書き上げるには熱量が要る。けれど、それを作品にするには冷徹な計算が要る。その落差に眩暈を覚えながら、半分になった原稿を見つめた。不思議と、十万文字あった頃よりも、今の五万文字のほうがずっと重たく感じる。小説を書くというのは、なんと難しく、そして厄介な営みだろうか。
(了)